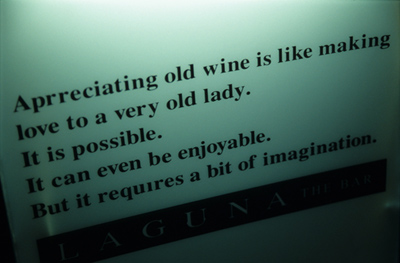
神戸、山の手。とびきり美味いカクテルを出すバーがある。いや、あった。
その店は、僕に「船」を連想させた。正方形の、どっしりしたドアを開けると、細長い店内には、有に20メートルはある長くて真っ直ぐなカウンター が、船の甲板のように横たわっている。バッファロー革のソファーが気持ちよく並び、磨き込まれたグラスと琥珀色の酒瓶が淡く光る。何組かのお客がソファー に深々と身を沈めながら、静かに話をしている。港町の山の手に、隠れ家のようにオープンした店。
僕にカクテルをつくってくれたのは、若いバーテンだった。多分、年齢は僕と幾らも変わらない。丸顔で、短い髪を撫でつけている。サッカー日本代表の、中田を太らせたような感じ。もしかしたら、バーテンダーをやるよりは、板場に立っていた方が、似合うかもしれない。
「これは?」
「カンパリです」
「それと?」
「カンパリと氷をシェイカーで少し」
「、、それだけ、、?」
料理の腕に才能があるように、バーテンにも才能がある。カクテルという飲み物は、材料もレシピもほとんどが厳密に決まっている。だからこそ、調製す る人間の腕前が際立つ。ただのカンパリと氷をシェイクしただけの一杯には、彼のセンスと技術が凝縮されていた。数ヶ月前、この店で彼のカクテルを飲んで、 僕は初めて知った。カクテルは「香る」のだ。
フランシス・アルバートというカクテルがある。ワイルド・ターキーとタンカレイをステアしただけの、単にそれだけのカクテル。しかし、混合比と温 度、そしてステアの技術がピッタリ合ったとき、奇跡が起きる。リキュールなど入っていないはずの琥珀色の液体が、突然、爽やかな柑橘系の芳香を放つのであ る。
「今日、会心の出来です」
カクテル・グラスに鼻をつっこんで、漂ってくる柑橘類の匂いを確かめている僕に向かって、彼はそう言った。フランシス・アルバートの奇跡は、その日、確かに起こった。僕はその夜、とことん彼と勝負することに決めた。
新しいお客が来て、新しいグラスが用意され、新しい飲み物がつくられる。真っ白に凍ったグラスに、美しく削られた透明の氷が入る。固く氷結した氷にアルコールが注がれた途端、パシッと音がして稲妻のような「ヒビ」が入る。この店は、きちんとした氷を使っている。
お客は何度も入れ替わり、夜は更けた。彼は僕たちにお酒をつくることを、楽しんでいた。僕たちも、時間を忘れて彼のカクテルが生み出す時間を楽しんだ。いい夜だった。
それから数ヶ月、久しぶりの神戸。その店に入った瞬間、空気が全く違っていた。あの心地の良い緊張感はなく、ただダラリとした眠そうな空気があった。そのバーテンの姿は、もうどこにもなかった。見たことのない店員が、シェイカーを振っていた。
1杯目のカクテルは、なんのひらめきも感じられないただの、混ぜ水だった。祈るような気分で、フランシス・アルバートを頼んだ。なぜかロックグラスに入って出てきた液体を一口だけ飲み、そして僕は席を立った。
僕はもう二度と、その店には行かないだろう。伝説は、失われてしまったのだ。
注:フランシス・アルバート(FRANCIS ALBERT)は、元々シナトラという名前のカクテル。南青山のバー、ラジオの尾崎浩司氏が考案したもの。


