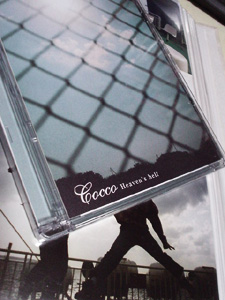Photo: "なんか憧れる、こういう機械" 2003. Tokyo, Japan, Sony Cyber-shot U10, 5mm(33mm)/F2.8 あるレーベルの人から「音楽は、宗教なんです。CD を買うお金はアーティストへのお布施なんです」という話を、聞いた。音楽産業を表すのに、こんなにぴったりした言い方はない。でも、最近の音楽は、ただ消 費されていくファーストフードの月替わりメニューのようにも思える。
いずれにしろ、音楽は芸術である以上に、「産業」なのだ。
もともと、オリジナルのパフォーマンスを聴くしかなかった音楽という芸術は、ラジオ、レコード等の複製・流通可能なメディアの出現によって、大きな 変貌を遂げた。かつて自分自身がパフォーマンスを行うことでしか対価を得られなかったアーティストは、たった一度の演奏を無限に複製することで、対数的な 富とプレゼンスを自身に集めることができるようになった。複製芸術の誕生だ。それによって、音楽は産業になった。でも、その「産業」が永遠に持続可能なも のだとは、誰も保証していない。事実、その輪郭はこの数年でだいぶ崩れたような気がする。
今世紀の音楽産業は、複製技術の進歩と広告プロモーションの洗練によって発展した。そして今、100% 同じコピーが作成可能なデジタル複製技術と、コミュニケーション・メディアの多様化に伴う嗜好・興味の細分化によって、そのビジネスの前提が崩れようとし ている。メディア技術の進化に依存して巨大な富を産んだ複製芸術は、皮肉なことに、その技術上の頂点に達した瞬間に、金の卵を産み続けることができなく なった。
じゃあ、音楽は無くなるのか。そんなことはない。既存の音楽産業の形態が崩れたら、日常から音楽がなくなってしまうかのような事を言う人もいるが、 そんなのはただの脅し。ビジネスがあって音楽が生まれたのではなくて、音楽がたまたまビジネスとして今のような形態の音楽産業を産んだだけの話。あるもの が崩れたら、あるものが生まれる。
例えば、最近割と面白くてインターネットラジオで合わせることが多い magnitune.com。 ここは、曲の売値の半分がアーティストに行くという、クリアな利益モデルをとっている。ネットを使って中間コストを省き、かつ、アーティストへの利益配分 率を上げることで、アーティストが一発ヒットをねらわなくても、食べられるような仕組みをつくっている。これから大切なのは、常識的な利益率と、選択肢の 提供ではないかと僕は考えている。もちろん、新しい試みは、そう簡単に成功しないだろう。でも、歯車が逆転することもないはずだ。