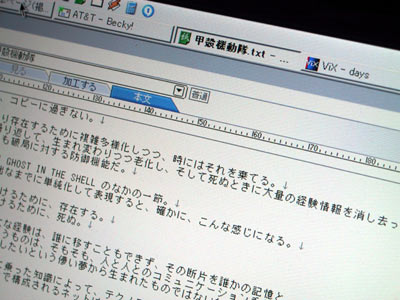最近増えてきたなぁ、と思いつつも、時に不愉快に感じるのが、日記系・テキスト系のサイトに対する批評・批判。そして、それに起因するネット上での論争・トラブルだ。
この手の話でよく言われるのが「ネットに公開している以上は、批判・批評の対象になることは甘受すべきだ」ということである。確かに、その通りなの だが、それは、公開処刑のようにみんなの目の前で吊るし上げて良い、ということでは無い。自分の目の前にあるのは、ドットを映すディスプレイ装置にすぎな いとしても、その向こう側には生身の人間がいる。論争とトラブルを引き起こすネット上での批判・批評には、生身の人間に対する基本的な配慮というものが、 欠落していることが多い。
そもそも、文章を使ったコミュニケーションというのは、難しい。ビジネスの世界ではメールが大活躍だが、表現にはとても気をつけて書く。一般的に は、メールを使って誰かを非難したり、論争をしたりすることは避けるようにする。それでも話しがおかしくなりそうだったら、電話するなり直接会うなりし て、修正をかける。なにも、論争やトラブルが目的ではないからだ。ところが、ネットの世界では誤解が生じたからといって、会って話すこともないし、電話も かけられない。あげく、論争・トラブル自体を目的にして面白がる人もいる。
僕は個人的には、インターネット上で安易に特定の個人サイトを批判・批評するのは良くないと思っている。そもそも、批判・批評といったようなもの は、強者に対して成してこそ意味がある。自分の楽しみに、ちょっと文章を書いているような人のサイトに、いちいち文句をつけたり、洒落っ気もない皮肉を 言ってみたりしたところで、なんの意味があるだろう。面白い批評・批判を書くことができる人は確かに居るけれど、この種の文章というのは非常に難しく、万 人に書けるものではない。
一方で、せっかくサイトを作ったのに、いろいろ言われて嫌な思いをしている管理者の人たちには、どうかそういう声は気にしないで更新を続けて欲し い。いくら文句を言われても、結局最後は更新を続けた者の勝ちである。羊ページも、過去にはいろんな評価サイトで、ボロボロに言われたけれど、そういうい ちゃもんサイトは、だいたい長続きしない。みなさんの更新を楽しみにしている読者の人が、かならずいるはずである。そういう人たちを大切にして欲しい。
ネット上の他人への配慮を欠いた行為、コンピュータ社会独特のトラブル、争い。そういうことが、インターネット利用者の増加とともに、間違いなく増えている。それを他人は他人、自分は自分ということで、勝手にやらせておくことが、本当に良い事なのか?と最近疑問に思う。
実社会の中でも、隣の誰かの行為を注意できなくなって久しい。電車の中で何かを注意しただけで、刺されるかもしれない。だから黙ってしまう。ネットの社会でも、そんな風にして皆が口を閉じてしまったら、これから先、どうなってしまうのだろう。
注1:ひ‐ひょう【批評】‥ヒヤウ 物事の善悪・美醜・是非などについて評価し論ずること。「作品を―する」「文芸―」[株式会社岩波書店 広辞苑第五版]
注2:ひ‐はん【批判】 1. 批評し判定すること。ひばん。 2. 人物・行為・判断・学説・作品などの価値・能力・正当性・妥当性などを評価すること。否定的内容のものをいう場合が多い。哲学では、特に認識能力の吟味を 意味することがある。「強い―を浴びる」[株式会社岩波書店 広辞苑第五版]