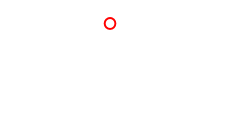某掲示板では、未だに「インディーズ板」にスレッドがあるトルネード竜巻(トル竜)が、なにやらapple.co.jpのトップを飾っていて驚く。そして、近所に買い物に行くのかというような格好で出ていることに更に驚く。
http://www.apple.com/jp/switch/macstory/tornado/index.html
このバンド名を言うと、必ず「トルネードと竜巻って同じ意味じゃない」と言われる。多分、それだけで聴く気をなくす人も多い(逆張りで興味を持つ人が残りの1割かな)んではないか。でも、その入り口でダメな人は、曲も多分ダメだから、それはそれで上手いのかもしれない。
2枚目のアルバムが出て(この人達はメジャーデビューしている)、手持ちのCDが増えてきたので、寄せ集めてCD-ROMに焼いてみたり。iPodのプレイリストで良いような気もするが、CDプレーヤーで聴くと全然音が違うから。
あと、部屋を更にかたづけて、キーボードをもう少しまともに使える位置に移す。なんで俺は88鍵なんて買ったのか。あまりにも長い。
芸術&写真&音楽の記事一覧(全 92件)
カメラのはじめ

思えば、写真が趣味になったのには、2つの理由があった。インターネットが登場したことと、CONTAX T2に出会ったことだ。
初めての海外旅行にもっていくためになにげなく買った、T2。その当時、レンジファインダーと一眼レフの区別も付いていなかったのだが、出来上がってきた写真を見た時には本当に驚いた。この絵は凄いな、と。
特に、ベネツィアで撮った何枚かの写真は、まともなカメラで写真を撮るのはせいぜいフィルム5本目程度の自分が撮ったとは思えないものだった。もちろん、背景にはベネツィアという都市の力があるのだが、それにしても、こんなものができてくるという驚きが写真の魅力に「はまらせた」のだ。
今から考えてみれば、水の風景というのはZeissのレンズにとっては、ある種独壇場で、なんの期待もてらいもなく切ったシャッターは、2度と撮れないほど無心ではあったのだと思う。今でも、その写真はとても大事だ。
もう一方のインターネットがなければ、これほど写真を撮ることは確かに無かったとも思う。文章と写真を組み合わせるということを、1997年ぐらいからやってきたのだが、あまり物理的なものとしての写真に囚われたくない自分としては、それをネットの上だけで展開するというのは魅力的であった。事実、フィルムスキャナとデジカメを本格的に使うようになってから、撮影枚数は劇的に増えたにもかかわらず、プリンタを使った数枚のお試し印刷をのぞき、僕は1枚たりとも紙焼きをしていない。
GRデジタル版
KyoceraのCONTAX撤退で、行き場のないデジカメ物欲はどこにいくのか。と思っていたら、あの時代の代表的なハイエンドコンパクトカメラRICHO GRがデジタル版になって帰ってくるという。
しかも、そのデビューのさせ方がちょっと洒落ていて、まずはblogが立ち上がった。読んでみると、担当者の声そのままというか、「生」感覚が強いエントリーが多い。
こういう、「消毒されていない」メッセージを出すというのは、会社としてはリスキーで、なかなかやりにくいと思うのだが、その決断には拍手を送りたい。
Kyocera CONTAXが、ユーザーの声を無視する形で、MMマウントを捨て、Nマウントに無理に移行して全く支持を得られず、結果として撤退の憂き目をみたことを考えると、カメラのような感性とか嗜好とかに依存する製品は、こういうハイタッチなコミュニケーションでつくっていくのが、これからは正解のように思う。
今までにもblogを使った商品展開・企画はあったが、デジカメでしかもここまで(ある種の層には)有名な製品では初めての試みではないだろうか。普通の宣伝企画と違って、予定調和というわけには行かないから、担当の方は大変だと思うが、それだけにネット上での関心も高い。僕も思わず、RICHOで知っている方に「凄いことやってますね!」とメールしてしまったぐらいだ。
なお、製品の発表会は、抽選で一般の人間も行ける模様。一応申し込んでおいた。GかRが付いたカメラを持って行くべし、という条件が付いている。CANON G2か?CONTAX RXか?まあ、いろいろあるから問題ないけど。