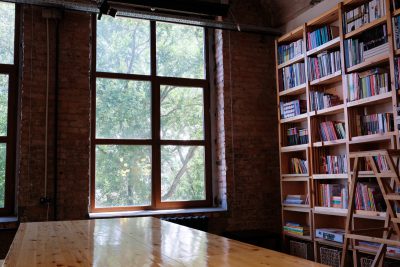性善説のイソターネットは、もう彼方に消えてしまったので、このサイトをhttpsにしなくてはいけないことは分かっていたのだけれど、なんかこうもの凄く面倒な気がして踏み切れないでいた。
結果として言えば、別にそんなに大変じゃ無かった。休日が、丸一日潰れたぐらいだった。サイトの中をいろいろ見ていると、自分が意外と、CSSの中とかで無意識にhttpを決め打ちしたりしていて、それはそれで、ちょっとショックだった。
友達がLINEで送ってきた、今の中学の技術の教材に関するtweetがあって、例文に<font size=”5″>とか清々しいタグが書いてあって、心が洗われた。このサイトは、HTMLの手打ちにわりと最後の方まで拘って、やっぱり大勢には行きたくないからNucleus CMSを試したり、使えなすぎてMovable Typeに日和ったり。いずれにしても、CMSを導入した時点で、HTML手打ちは諦めたのだけれど、それから14年経って、、まだこの国はHTML4を教えるか。
日本の義務教育は、その成り立ちから考えても固定化された知識を教える場所、と多分定義されていて、習っていない算数の解き方の利用の是非とかそういう議論もそこの辺りから来ている気がする。でも、もうそんな時代じゃ無いし、(その辺りの歴史は詳しくないのだけれど)明治維新とかそういう知識体系が大きく変わって、色んな事を取り入れなきゃいけないタイミングでは、もっと違った学問の形があったはずだ。
少なくとも今は、固定化された知識だけでは、太刀打ちが出来ない。多少のばらつきは許容してでも、新しいものを教えなければ、大変な事になってしまう。でも、HTML5を教えられる人が中学校の先生になるのか、というとそれは現実的に無いし、HTML5を教員採用の基準にする、とかやったら更に恐ろしい事になるだろう。そこを解決するのは、多分マニアなテクノロジー好きの学生が独学でやっているような、そんなやり方だと思う。
それにしても教科書の話。じゃあ、とりあえず技術の教科書じゃ無くて、HTMLの歴史って事で教えればいいんじゃないの、と友達は言っていたけれど、それだったら侍魂とかも載せないと、歴史の教科書としては知識に偏りが出るんじゃ無いか、そんな危惧もあるね。(僕は読んでなかったけど)